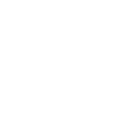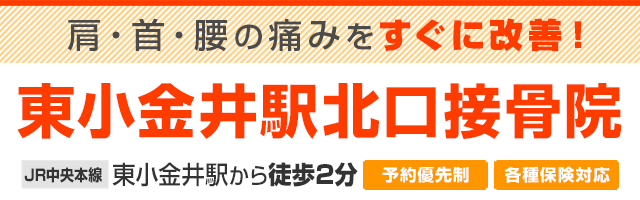巻き肩

こんなお悩みはありませんか?

長時間のデスクワークやスマートフォンの使用で肩が前に出て丸まっていると感じる
首や肩の筋肉が常に緊張していて、肩甲骨が外側に広がっている気がする
肩こりや頭痛が慢性的に続いている
姿勢が悪いと指摘されることがある
呼吸が浅く、少し動いただけで疲れやすい
胸が閉じたような感覚があり、呼吸がしづらい
ストレッチや運動をしてもなかなか巻き肩がよくならない
デスクワークの姿勢が原因で、肩まわりの違和感が続いている
日常生活で姿勢を意識しようとしてもすぐに戻ってしまう
肩甲骨の動きが悪く、背中が固まっているように感じる
巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩の予防と軽減には、適切なストレッチやエクササイズが効果が期待できます。胸を開くストレッチや肩甲骨を寄せるエクササイズを取り入れることで、筋肉の緊張を和らげ、正しい姿勢を目指すことができます。具体的な方法としては、壁に背中をつけて両肘を直角に曲げ、肩甲骨を寄せる動作や、手を腰に当てて胸を張るストレッチがあります。また、デスクワーク時には椅子の高さやパソコンの位置を調整し、こまめに休憩を取ることも大切です。
さらに、日常生活での姿勢への意識を高めることも必要です。正しい姿勢を意識的に保つことで、巻き肩の予防や軽減が期待できます。定期的な運動やストレッチを習慣化し、継続して取り組むことで、健康的な姿勢を維持することが可能です。巻き肩に関する知識を深め、日常に取り入れることで、お身体の負担を減らすことにつながります。
症状の現れ方は?

巻き肩の原因は肩甲骨の外転変位に加え、猫背になると胸椎の後弯増強が加わり、肩甲挙筋や僧帽筋上部線維の筋緊張により肩甲骨が挙上しやすくなります。スマートフォンの画面を集中して見ると、無意識のうちに首が下を向き、肩が丸まってしまいます。デスクワークで長時間パソコンに向かっている方も、肩を前に突き出した状態が続くため、肩甲骨が外側へ広がり巻き肩につながりやすいといわれています。
また、「横向き寝」も巻き肩の要因のひとつです。横向きで寝ていると、重力の影響で肩に負担がかかり、肩の位置が前へスライドしやすくなります。そのような姿勢を続けていると、筋肉が硬くなり、巻き肩が習慣化しやすくなります。
その他の原因は?

巻き肩の原因として、背中にある僧帽筋や肩甲挙筋が伸びた状態で硬くなり、肩甲骨の動きが制限されることが挙げられます。肩の動きが悪くなると血行も滞りやすくなり、筋肉に十分な酸素が届かず老廃物がたまりやすくなります。その結果、筋肉が硬直し、肩こりや腰痛などが起こりやすくなります。
また、反り腰といわれた方も巻き肩の要因となり得ます。反り腰により腰痛が出ると、再び前かがみの姿勢になり、肩こりや猫背が進行し巻き肩になることもあります。肩こりがつらくなると、反り腰の姿勢に戻りやすく、肩こりと腰痛を繰り返してしまう悪循環が生まれる可能性があります。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩を放置すると、背中まで曲がり、猫背の傾向が強くなる場合があります。肩に前方向への負担がかかることで肩こりを引き起こしたり、ストレートネックの原因になることがあります。ストレートネックになると、肩の痛みだけでなく、血流の悪化により睡眠の質の低下や疲労感が残りやすくなり、めまいや頭痛などの不調につながる場合があります。
さらに、巻き肩は自律神経の乱れを引き起こすこともあります。巻き肩の方には筋膜の緊張が見られることが多く、筋膜が硬くなると神経が圧迫され、自律神経のバランスが崩れる可能性もあります。
当院の施術方法について

当院では、肩甲骨に関与する肩甲挙筋や僧帽筋の緊張を和らげるために、肩甲骨はがしを行っています。また、胸周りの大胸筋や小胸筋の緊張により肩が内に巻いてしまうことから、その硬さを取り除くための上半身ストレッチや猫背矯正を行っております。
お身体の歪みに着目した全身矯正も行っており、筋緊張の緩和や姿勢を整え、身体への負担を軽減することを目指しています。巻き肩によって筋肉が硬くなり血流が滞ることから、血行促進のための施術も取り入れております。筋肉の硬さが和らぎ、循環が整うことで、疲労感の軽減が期待できます。
軽減していく上でのポイント

<ストレッチとエクササイズ>
●胸を開くストレッチ
壁に背中をつけて両肘を直角に曲げ、肩甲骨を寄せる動作を行います。
●肩甲骨を寄せるエクササイズ
手を腰に当てて胸を張るストレッチも効果が期待できます。
●首と肩のストレッチ
首を左右にゆっくりと回したり、肩を上下に動かすエクササイズも取り入れましょう。
<正しい姿勢の意識>
●デスクワーク時の姿勢
椅子の高さやパソコンの位置を調整し、画面が目の高さになるように心がけます。
●こまめな休憩
長時間同じ姿勢を避けるため、1時間に1回は立ち上がって体を動かしましょう。
<生活習慣の見直し>
●適度な運動
日常的にウォーキングやストレッチを取り入れ、身体全体のバランスを整えることが大切です。
●姿勢サポートグッズの利用
姿勢矯正ベルトやクッションを活用するのもおすすめです。
<リラックスとストレスケア>
●リラクゼーション
ヨガや深呼吸、瞑想などを取り入れて筋肉の緊張を和らげましょう。
●接骨院での施術
専門家の手による施術を受けることで、筋肉の緊張を緩和し血流の促進が期待できます。
監修

東小金井駅北口接骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:千葉県鎌ケ谷市
趣味・特技:旅行、マリンスポーツ